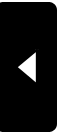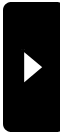2009年10月28日
レクリエーション・インストラクターへの道
第19期 レクリエーション・インストラクター養成講座
10月25日(日) 高松市ふれあいセンター「勝賀」 にて
春に開講し、 暑い夏が過ぎ
「勝賀」前の並木は 紅葉が始まっていました
10回コースの 6回目 -後半ー です
【午前の部】
レクリエーション事業計画 です
講師は 小山雅史 先生
まず ジャンケンゲームで 心と体を解します
あなたは ジャンケンが 強いほうですか?
「強いと思う」 「普通だと思う」 「弱いと思う」
自分が思うグループに 分かれます
あくまでも 自己申告です
それでは
いろんな人とジャンケンをして 5回勝った人から順に 椅子に座ります
さて どんな結果になったのでしょう?
自己申告のとおり も あれば
自己満足のとおり も あり でした
たかが ジャンケン されど ジャンケンで
盛り上がる 受講生…

3班に分かれてのグループ討議
自分にとってのレクリエーションとは
・心の休息、気分転換、楽しいことをする
・ストレス解消、人と関わることでリフレッシュできる など
レクリエーション事業とは
・ノーマナイゼーション
・無理をしない
・主催者も参加者も共に楽しむ
・楽しみを広める
PLAN(計画) → DO(実施) → CHECK(評価) → ACTION(再行動)
支援者と参加者が共に有意義な 両義性 をもつような 事業を展開する
小山先生の 熱心な講義に 聴き入ります

【午後の部】
レクリエーション活動の安全管理
講師は 長松広志 先生 です
危険予知トレーニング では
飯ごう炊飯場面を描いたイラストで 危険だと思う箇所を
グループで討議し発表します。
・火を焚いている傍で、ふざけあっている
・熱い鍋をよそ見をしながら運ぶ
・蒔き割りをした後の危険な用具を出しっぱなしにしている
・熱い飯ごうを素手で触ろうとしている
・マッチや新聞を火の傍に置いている
そして 怪我や事故を予知し、防ぐためにはどうするか ディスカッションします
レクリエーション活動における安全管理の必要性と
方法について学習します
☆事故を未然に防ぐための視点、注意の方法を確認する
よく夏のプールで、子どもが飛び込み、それを見た監視員が
ホイッスルを吹いて注意をする光景を目にする。実は、これでは
飛込みによる事故は未然に防ぐことはできない。 飛び込みに
よる事故を防ぐためには、子どもの行動に目を配り、飛び込む前
にホイッスル等で止めなくてはならない。
スタッフは事故につながる行動をあらかじめ想定し、そうした
行動の気配や素振り、注意の方法を確認する必要がある。
□危険の捉え方 =活動に必要とされる危険=
例えば、子どもが自分の実力と見比べて、「この高さは危ない」
など判断が出来る危険である。子どもたちは遊びの中で、こうした
危険を経験し、成長する。自然の中で行われるレクリエーション活
動では、ある程度の危険を経験させて、体験的に危険を予知し、
回避する能力を養っていく。レクリエーションを実施する中では、こ
うした活動やプログラムのねらいに伴い、ある程度認めていくべき
危険がある。
事業を行う上で、あらかじめ想定できる危険を把握し、スタッフの対応能力
や参加者の対応力も合わせ、事故を未然に防ぐための視点や注意の方法
を確認することが重要である。
-レクリエーション支援の基礎ーテキストより抜粋
ちょっと 休息
ちょっと細工している 針金です

針金 と ペンチ …

こんな風に 曲げます

わぁ~! 回っています(右側) 「針金駒」?!

中心がぶれると 回りません
「わ~! 回った回った!」 「すご~!!」
たかが 針金 されど 針金で
盛り上がる 受講生…
講義の合間に 簡単に作れて 楽しめるクラフトで
受講生の心を 和ませてくれます
私達 受講生は
この日も たくさんの知識を 体いっぱいに詰め込み
着実に レクリエーション・インストラクターへの道を
歩み続けているのであります
ロビー正面の奥 左側の掲示に
面白いものを 見つけました
「つもり違い」 です

なるほど~ ← わかった つ・も・り…
10月25日(日) 高松市ふれあいセンター「勝賀」 にて
春に開講し、 暑い夏が過ぎ
「勝賀」前の並木は 紅葉が始まっていました
10回コースの 6回目 -後半ー です
【午前の部】
レクリエーション事業計画 です
講師は 小山雅史 先生
まず ジャンケンゲームで 心と体を解します
あなたは ジャンケンが 強いほうですか?
「強いと思う」 「普通だと思う」 「弱いと思う」
自分が思うグループに 分かれます
あくまでも 自己申告です
それでは
いろんな人とジャンケンをして 5回勝った人から順に 椅子に座ります
さて どんな結果になったのでしょう?
自己申告のとおり も あれば
自己満足のとおり も あり でした

たかが ジャンケン されど ジャンケンで
盛り上がる 受講生…
3班に分かれてのグループ討議
自分にとってのレクリエーションとは
・心の休息、気分転換、楽しいことをする
・ストレス解消、人と関わることでリフレッシュできる など
レクリエーション事業とは
・ノーマナイゼーション
・無理をしない
・主催者も参加者も共に楽しむ
・楽しみを広める
PLAN(計画) → DO(実施) → CHECK(評価) → ACTION(再行動)
支援者と参加者が共に有意義な 両義性 をもつような 事業を展開する
小山先生の 熱心な講義に 聴き入ります
【午後の部】
レクリエーション活動の安全管理
講師は 長松広志 先生 です
危険予知トレーニング では
飯ごう炊飯場面を描いたイラストで 危険だと思う箇所を
グループで討議し発表します。
・火を焚いている傍で、ふざけあっている
・熱い鍋をよそ見をしながら運ぶ
・蒔き割りをした後の危険な用具を出しっぱなしにしている
・熱い飯ごうを素手で触ろうとしている
・マッチや新聞を火の傍に置いている
そして 怪我や事故を予知し、防ぐためにはどうするか ディスカッションします
レクリエーション活動における安全管理の必要性と
方法について学習します
☆事故を未然に防ぐための視点、注意の方法を確認する
よく夏のプールで、子どもが飛び込み、それを見た監視員が
ホイッスルを吹いて注意をする光景を目にする。実は、これでは
飛込みによる事故は未然に防ぐことはできない。 飛び込みに
よる事故を防ぐためには、子どもの行動に目を配り、飛び込む前
にホイッスル等で止めなくてはならない。
スタッフは事故につながる行動をあらかじめ想定し、そうした
行動の気配や素振り、注意の方法を確認する必要がある。
□危険の捉え方 =活動に必要とされる危険=
例えば、子どもが自分の実力と見比べて、「この高さは危ない」
など判断が出来る危険である。子どもたちは遊びの中で、こうした
危険を経験し、成長する。自然の中で行われるレクリエーション活
動では、ある程度の危険を経験させて、体験的に危険を予知し、
回避する能力を養っていく。レクリエーションを実施する中では、こ
うした活動やプログラムのねらいに伴い、ある程度認めていくべき
危険がある。
事業を行う上で、あらかじめ想定できる危険を把握し、スタッフの対応能力
や参加者の対応力も合わせ、事故を未然に防ぐための視点や注意の方法
を確認することが重要である。
-レクリエーション支援の基礎ーテキストより抜粋
ちょっと 休息
ちょっと細工している 針金です
針金 と ペンチ …
こんな風に 曲げます
わぁ~! 回っています(右側) 「針金駒」?!
中心がぶれると 回りません
「わ~! 回った回った!」 「すご~!!」
たかが 針金 されど 針金で
盛り上がる 受講生…
講義の合間に 簡単に作れて 楽しめるクラフトで
受講生の心を 和ませてくれます
私達 受講生は
この日も たくさんの知識を 体いっぱいに詰め込み
着実に レクリエーション・インストラクターへの道を
歩み続けているのであります

ロビー正面の奥 左側の掲示に
面白いものを 見つけました
「つもり違い」 です
なるほど~ ← わかった つ・も・り…
Posted by レクちゃん at 01:00│Comments(0)
│お勉強会